
 院長:高木
院長:高木お気軽にご相談ください!

 院長:高木
院長:高木お気軽にご相談ください!


肩甲骨の真ん中あたりに感じる痛みや重だるさ、もしかすると日常の何気ない習慣が影響しているかもしれません。実はこの部位の痛みには、筋肉の問題だけでなく姿勢や内臓の状態、さらには神経系のトラブルまで、さまざまな要因が関わっているといわれています。ここでは、考えられる主な原因を詳しく見ていきましょう。
肩甲骨の真ん中周辺には、僧帽筋や菱形筋といった筋肉が集まっています。長時間のデスクワークやスマホの操作で同じ姿勢が続くと、これらの筋肉に負担がかかり、血行不良や筋肉の硬直を招きやすくなるでしょう。
特に菱形筋は背中の深い部分にある筋肉で、肩甲骨を背骨側に引き寄せる役割を担っています。肩甲骨を動かさない姿勢を続けていると硬くなり、痛みや違和感を引き起こすことがあるようです。
猫背や巻き肩といった前傾姿勢も、肩甲骨の真ん中に痛みをもたらす大きな要因のひとつです。体が前のめりになると肩甲骨が外側に引っ張られた状態が続き、肩甲骨の内側に負担が集中してしまいます。
この状態が長引くと筋肉が疲労し、慢性的な張りや痛みにつながりやすいといわれています。また、姿勢の崩れによって背骨の自然なカーブが失われると、椎間板や関節にも過剰な圧力がかかることがあります。
意外に思われるかもしれませんが、肩甲骨の痛みが内臓からのサインである場合もあるんです。これは関連痛と呼ばれるもので、内臓の不調が他の場所に痛みとして現れる現象を指します。例えば、胆石症では右の肩甲骨の下に痛みが生じることがありますし、心臓や膵臓の問題が背中に違和感をもたらすケースも報告されています。
頸椎や胸椎のゆがみによって神経が圧迫されると、肩甲骨周辺に痛みやしびれが生じることがあります。また、背骨の自然な配列が崩れることで、肩甲骨の真ん中に負担が集中しやすくなるでしょう。姿勢はそんなに悪くないのに痛むという方は、神経系の問題を視野に入れてみることも大切かもしれません。
#肩甲骨の痛み #僧帽筋と菱形筋 #猫背改善 #関連痛 #姿勢と筋肉


肩甲骨の真ん中が痛むとき、単なる筋肉疲労だと思いがちですが、実は背景にさまざまな疾患が隠れているケースもあるんです。ここでは、考えられる主な疾患とそれぞれの特徴について詳しくお伝えしていきます。
筋筋膜性疼痛症候群、通称MPSは、筋肉内にできるトリガーポイントと呼ばれる硬いシコリが痛みの引き金となる状態です。トリガーポイントを押すと、その場所だけでなく離れた部分にまで痛みが広がることがあり、これを関連痛と呼んでいます。
肩甲骨の真ん中にトリガーポイントができると、背中全体に違和感が広がったり、場合によってはめまいなどの自律神経症状が現れることもあるといわれています。日常的な動作の繰り返しや過度な筋肉の使用、ストレスなどが原因となって形成されやすいようです。
背骨の椎間関節に問題が生じる椎間関節症では、腰を反らしたりひねったりする動作で痛みが強まる傾向にあります。特に前かがみから体を戻すときに痛みを感じやすく、背骨の真ん中あたりに痛みが集中することもあるでしょう。
一方、棘上靭帯炎は背骨の後方にある棘上靭帯という靭帯が炎症を起こしている状態で、腰の真ん中を押すと痛みが生じたり、前かがみで激痛が走ったりするのが特徴です。デスクワークやスポーツで何度も腰部に負担がかかる方に多く見られる傾向があるようです。
胸椎椎間板ヘルニアは、背中から胸にかけての痛みやしびれが主な症状で、初期には軽い背中の違和感から始まることが多いとされています。
症状が進行すると、下半身の筋力低下や歩行困難、排尿障害といった重篤な症状につながることもあるようです。背中の痛みとともに体のどこかの感覚が鈍く感じたり、足がもつれたりする場合は注意が必要かもしれません。
内臓の問題が肩甲骨に痛みをもたらすこともあります。胆石症では、特に脂肪分の多い食事の後に右の肩甲骨の下に激しい痛みが生じることがあり、背中に抜けるような放散痛を伴うケースも報告されています。
心筋梗塞や狭心症といった心臓疾患では、胸痛だけでなく背中の左上部に痛みが広がることもあるといわれています。こうした内臓疾患による痛みは、冷や汗や呼吸困難、吐き気といった症状を伴う場合が多いため、早めの医療機関への相談が大切でしょう。
| 疾患名 | 主な特徴 |
|---|---|
| 筋筋膜性疼痛症候群(MPS) | 押すと痛む硬いコリがあり、周囲に痛みが広がる |
| 椎間関節症・棘上靭帯炎 | 体を反らしたりひねったりする動作で痛みが増す |
| 胸椎椎間板ヘルニア | 背中から胸にかけての痛みとしびれ |
| 内臓疾患 | 冷や汗や吐き気などの全身症状を伴う |
見分けるポイントとして、痛みが動作と連動しているか、全身症状があるかを観察することが役立つでしょう。
#筋筋膜性疼痛症候群 #トリガーポイント #椎間関節症 #胸椎ヘルニア #内臓関連痛


肩甲骨の真ん中が痛むときは、自宅でもできるセルフケアを取り入れることで痛みの軽減が期待できます。無理をせず、体の声を聞きながら少しずつ実践してみてください。
まず覚えておいていただきたいのは、強い痛みを感じているときは無理に動かさないほうがよいということです。急性の炎症が起きている可能性もあるため、無理にストレッチをすると逆効果になることがあります。患部を安静に保ち、痛みが落ち着くまでは激しい運動や重い荷物を持つことは控えましょう。
痛みが和らいできたら、肩甲骨周りのストレッチを始めてみてはいかがでしょうか。
これらのストレッチを毎日の習慣にすることで、肩甲骨まわりの筋肉が柔軟になるといわれています。
デスクワーク中は長時間同じ姿勢が続くため、筋肉が緊張して血管や筋肉が圧迫されやすくなります。パソコン作業のときは背筋をまっすぐに伸ばし、肩が前に出ないよう意識してみてください。椅子に深く腰掛け、膝が90度になるように調整すると骨盤が安定し、肩甲骨への負担も軽減されるでしょう。
肩甲骨の痛みに対しては、状態に応じて温めるか冷やすかを使い分けることがポイントです。お風呂に入ったときに心地良さを感じるなら温め、強い痛みや疼痛を感じるなら冷やすとよいといわれています。慢性的な筋肉の硬さによる痛みには、蒸しタオルや入浴で温めて血行を促進する方法が有効なようです。一方、腫れや急性の炎症がある場合は、冷やすことで痛みが和らぐケースもあるでしょう。
ウォーキングやジョギングをするときに肘を前後に意識的に動かすだけでも、肩甲骨周りの血流改善につながります。肩より上に手を伸ばす動作を日常的に取り入れることで、肩周りの運動不足を解消できるといわれています。また、40℃前後のぬるめの湯に10〜15分ほど浸かることで全身の血行が良くなり、肩甲骨の痛みも和らぐことが期待できるでしょう。
#肩甲骨ストレッチ #セルフケア #姿勢改善 #温冷使い分け #血流改善


肩甲骨の真ん中に痛みを感じたとき、ただの筋肉疲労なのか、それとも医療機関で相談すべきなのか迷うこともあるでしょう。ここでは、受診が必要なサインと適切な診療科の選び方を詳しくお伝えします。
まず覚えておいていただきたいのは、息苦しさや胸の圧迫感を伴う場合です。突然激しい痛みが起こったり、痛みが30分、1時間と持続的に強くなる場合は、内科的な疾患を疑うべきかもしれません。特に息を吸ってみて吸えないほど肩甲骨が痛いのであれば要注意です。
食後に右の肩甲骨の下に激しい痛みが生じる場合は、胆石症の可能性も考えられます。右の肋骨の下に差し込むような痛みを感じ、背中に抜けるような痛みを伴うこともあるようです。また、冷や汗や吐き気、発熱といった全身症状を伴う場合は、早急に医療機関へ相談することが大切でしょう。
2週間以上続く持続的な痛みがある場合は、医療機関の受診を検討する必要があるといわれています。特に安静時でも痛みが続く場合や、夜間に痛みが悪化する場合は注意が必要です。また、眠れないほど強い痛みが続く場合も、早めの相談が望ましいでしょう。
診療科の選び方にはコツがあります。
| 症状の特徴 | 適切な診療科 |
|---|---|
| 肩や首を動かすと痛みが悪化する、ストレッチで楽になる、お風呂で温まると楽になる | 整形外科 |
| 突然激しい痛みが出て持続的に強くなる、息が吸えないほど痛い | 内科 |
| 胸の痛み、息切れ、呼吸困難を伴う | 循環器内科・救急外来 |
| 頭痛やめまいを伴う | 脳神経外科 |
| 吐き気や発熱がある | 内科 |
心筋梗塞や狭心症といった心疾患の可能性がある場合は、循環器内科や救急外来への相談が必要といわれています。
整形外科では、レントゲンやMRI、CTなどの画像検査によって、骨や筋肉、靭帯、椎間板の状態を確認することができます。内科では血液検査や超音波検査によって、内臓の状態を詳しく調べることが可能です。精密な検査が必要な場合には、適切な検査機器が備わっている医療機関を選ぶことが重要でしょう。
#受診タイミング #診療科の選び方 #緊急症状 #整形外科と内科 #医療機関選び
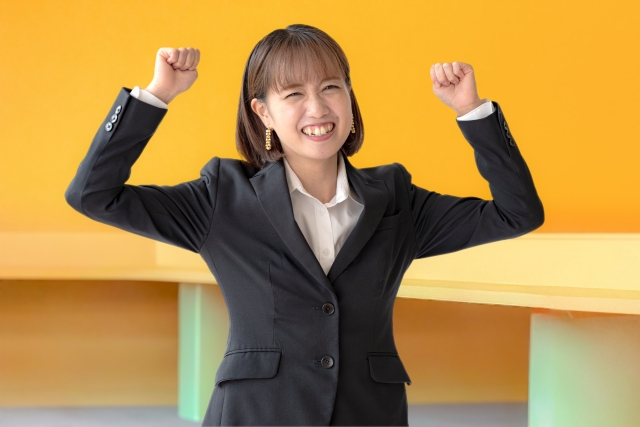
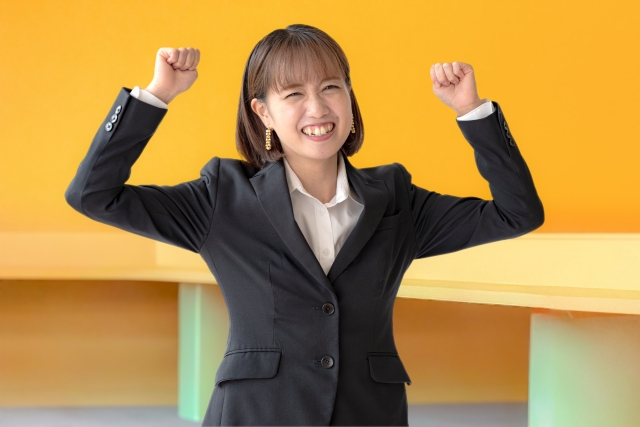
肩甲骨の真ん中の痛みを防ぐには、日々の生活習慣を少しずつ見直すことが何より大切です。ちょっとした工夫を積み重ねることで、痛みの予防につながるでしょう。
デスクワーク中は、1時間ごとに立ち上がって肩を回すなど、こまめに体を動かす習慣をつけることが推奨されています。同じ姿勢が続くと筋肉が緊張し、血管や神経が圧迫されやすくなるため、意識的に姿勢を変えることが重要です。軽いストレッチやウォーキングを1時間に1回行うことで、血行が改善され、肩甲骨まわりの痛みを防ぎやすくなるでしょう。
スマホやパソコン作業を長時間続けると、首が前に出た状態のストレートネックやスマホ首になりやすく、首や肩の筋肉に常に緊張を強いることになります。パソコンを使う際は、画面の高さを目線と同じかやや下に調整し、背筋をまっすぐに伸ばして肩が前に出ないよう気をつけてみてください。スマホを見るときも、なるべく目線の高さまで持ち上げることで首への負担を軽減できるといわれています。
仰向けで寝ているときの理想的な姿勢は、立っているときと同じように首の骨や背骨のS字カーブが保たれている状態です。枕が高すぎると肩まわりの筋肉に負荷がかかり、低すぎると頸椎を支えられずに首や肩の痛みの原因になってしまいます。柔らかすぎる枕は頭が沈んで正しい寝姿勢をキープできないため、やや硬めで首をしっかり支えられるものを選ぶとよいでしょう。
椅子に座るときは、背もたれに頼りすぎず骨盤を立てるように意識すると、肩甲骨が正しい位置に保たれやすくなります。腰にクッションを当てることで、腰や肩への負担を軽くすることもできます。
ストレスや疲労が蓄積すると、筋肉が緊張しやすくなり肩甲骨周辺の痛みにつながることがあります。質の良い睡眠を確保することで、体の回復が促進され、筋肉の緊張も和らぐといわれています。夜更かしを避け、規則正しい生活リズムを整えることも、肩甲骨の痛みを防ぐ上で大切なポイントでしょう。
肩甲骨を柔軟に動かすことで、猫背や巻き肩を改善し、美しい姿勢をキープできます。ウォーキングやヨガなど、肩甲骨を動かす運動を習慣にすると姿勢が整いやすくなるといわれています。歩くときは、あごを引き背筋を伸ばして胸を張ることで、肩のこりや痛みの予防につながるでしょう。毎日のストレッチやエクササイズを習慣にし、正しい姿勢を意識することが健康的な体を維持する秘訣です。
#日常習慣の見直し #姿勢改善 #枕の選び方 #ストレス管理 #ストレッチ習慣
肩甲骨の真ん中が痛む原因は、筋肉の緊張や姿勢の乱れといった日常的な要因から、内臓疾患や神経の圧迫といった深刻な問題まで多岐にわたります。筋筋膜性疼痛症候群や椎間関節症、胸椎椎間板ヘルニアなど、さまざまな疾患の可能性を考慮することが大切です。
自宅でのセルフケアとしては、痛みが強いときは無理せず安静にし、症状が落ち着いてから肩甲骨周りのストレッチや正しい姿勢の維持、温冷療法を取り入れることが効果的でしょう。また、1時間ごとに体を動かす習慣や、パソコン・スマホ使用時の姿勢改善、適切な枕選びなど、日常生活での工夫も痛みの予防につながります。
ただし、息苦しさや胸の圧迫感、冷や汗や吐き気といった全身症状を伴う場合、2週間以上痛みが続く場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。症状の特徴に応じて整形外科、内科、循環器内科などを適切に選び、必要な検査を受けることで、痛みの根本原因を明らかにできます。
肩甲骨の痛みは放置せず、適切な対処と予防を心がけることで、快適な日常生活を取り戻すことができるでしょう。