
 院長:高木
院長:高木お気軽にご相談ください!

 院長:高木
院長:高木お気軽にご相談ください!
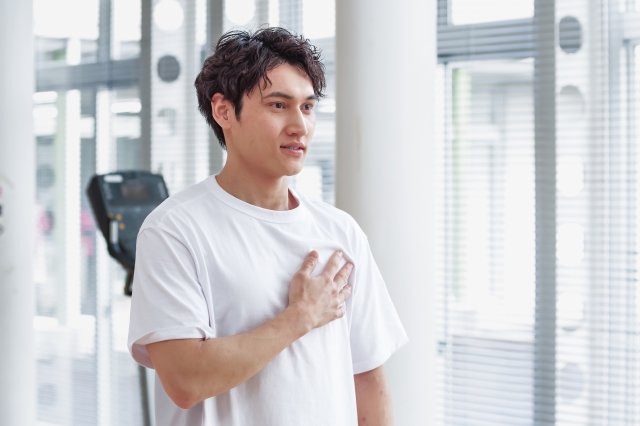
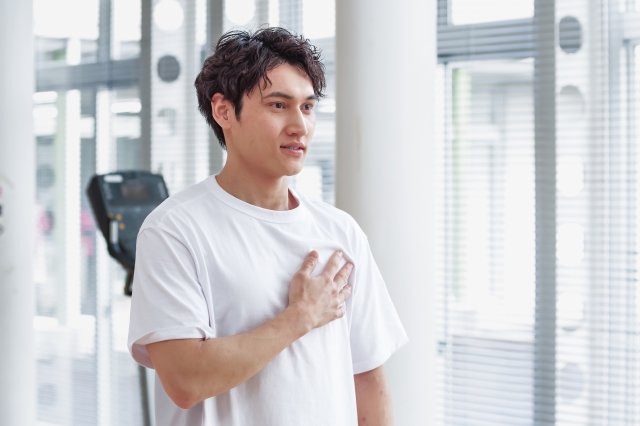
背骨は頭から腰まで続く長い骨の連なりですが、その中で胸の部分にあるのが胸椎と呼ばれる骨です。全部で12個あり、上から順番にT1からT12という番号で呼ばれています。頸椎という首の骨が7個、腰椎という腰の骨が5個あって、胸椎はちょうどその間に位置しているんですね。
| 部位 | 個数 | 位置 |
|---|---|---|
| 頸椎 | 7個 | 首の部分 |
| 胸椎 | 12個(T1-T12) | 胸の部分 |
| 腰椎 | 5個 | 腰の部分 |
胸椎は椎体と呼ばれる円柱状の骨が中心にあり、その後ろ側に椎弓というアーチ状の構造がついています。背中側には棘突起という突起があり、左右には横突起が伸びているんです。この形が胸椎ならではの特徴で、肋骨とつながるための仕組みを持っているところが他の背骨と違うポイントになります。
胸椎には肋骨が左右12対接続しており、肋骨は前側で胸骨という骨とつながります。この胸椎と肋骨と胸骨が一体となって作る籠のような構造を胸郭といい、心臓や肺といった大切な臓器を守る役割を果たしているわけです。胸椎と肋骨は関節でつながっているため、呼吸の時に胸郭全体が動けるようになっていますね。
背骨を横から見ると、首は前に、胸は後ろに、腰は前にとカーブを描いています。胸椎は元々後ろ側に丸くなる生理的後弯という形をしていて、このS字カーブがあるおかげで体重の負荷をうまく分散できるようになっているんです。ただし胸椎の丸みが強くなりすぎると猫背の原因になってしまうため、適度なカーブを保つことが良い姿勢には欠かせません。
#胸椎 #背骨の構造 #胸郭 #生理的後弯 #T1からT12


胸椎の周りには背中を支える大きな筋肉のグループがついています。その代表が起立筋群で、腸肋筋、最長筋、棘筋という3つの筋肉から構成されているんです。これらの筋肉は背骨に沿って縦に走っていて、背中を反らす伸展動作や姿勢を保つ働きを担っています。立っている時や座っている時に体をまっすぐ保てるのは、この起立筋群がしっかり機能しているからなんですね。
起立筋群よりも深いところには多裂筋や肋骨挙筋といった深層筋が存在します。多裂筋は背骨の椎骨と椎骨をつなぐように走っていて、背骨の安定性を高める重要な役割を果たしているわけです。肋骨挙筋は胸椎から肋骨に向かって伸びており、背中を伸ばす動作や肋骨を持ち上げる働きがあります。これらの深層筋は目立たない存在ですが、体幹の細かなコントロールには欠かせない筋肉といえるでしょう。
胸椎には呼吸に関わる筋肉も多く付着しています。
これら3層の肋間筋が胸郭の動きをサポートしている
首の部分には斜角筋があって、深い呼吸をする時に補助的に働きます。上後鋸筋は胸椎上部から肋骨に付着して吸気を助け、下後鋸筋は胸椎下部から肋骨に向かい呼気を補助する働きがあるんです。これらの補助筋群は普段の呼吸ではあまり使われませんが、運動時や努力して呼吸する場面で活躍する筋肉になります。
#起立筋群 #多裂筋 #呼吸筋 #横隔膜 #肋間筋


背中を反らす動きを伸展といいますが、この動作には腸肋筋、最長筋、棘筋、多裂筋といった背筋群が大きく関わっています。胸を張る姿勢や上を向く動作をする時、これらの筋肉が協力して背骨を後ろ側に動かしているわけです。
デスクワークが続いて背中が丸まった状態から体を伸ばす時も、この背筋群が活躍しています。逆にこれらの筋肉が硬くなったり弱くなったりすると、良い姿勢を保つことが難しくなってしまうんですね。
体を捻る回旋動作において、胸椎は背骨の中で最も得意な部分なんです。腰椎は椎骨の形状から回旋が苦手で、無理に腰を捻ろうとすると痛めてしまう可能性があります。
ゴルフのスイングや振り返る動作では、本来胸椎が回旋の役割を担うべきなのですが、胸椎の動きが悪くなると腰椎に負担がかかってしまうわけです。胸椎は椎骨が一つ一つ少しずつ回転して、全体で大きな捻り動作を生み出しているんですね。
横方向に体を曲げる側屈動作も胸椎の重要な動きの一つです。例えば右側に体を傾けると左の脇腹が伸びるのですが、日常生活の癖で無意識に片側へ傾いてしまうことがあります。傾きが続くと重心バランスが崩れて、傾いている側に体重が乗りやすくなるんです。
歩く時にも片側の足に負担がかかりやすくなり、膝や腰の痛みにつながることも考えられます。
肩甲骨の動きと胸椎は密接につながっています。肩甲骨を背骨側に寄せると背中が伸びやすく、前側に動かすと背中が丸まりやすくなるんですね。腕が前に出れば肩甲骨も前についていき、胸椎も丸くなってしまうわけです。この連動性を利用すれば、回旋動作もより大きく行えるようになります。
#胸椎の伸展 #回旋動作 #側屈 #肩甲骨連動 #体幹の動き


胸椎周辺の筋肉は日常的な姿勢を保つために働いています。胸椎は元々後ろに丸いカーブを持っているのですが、この丸みが過剰になると猫背や円背といわれる状態になってしまうんです。
スマートフォンを長時間見ていると頭が前に出て、それに伴って胸椎も前方向に丸まってきます。前側に丸まる筋肉が硬くなり、背中を伸ばす筋肉が働きにくくなることで、姿勢が崩れやすくなるわけですね。適切な後弯を保つためには、胸椎周辺の筋肉バランスが大切になります。
呼吸動作には胸椎周辺の多くの筋肉が関わっています。
肩甲骨の位置は胸椎の状態に大きく影響します。デスクワークで腕が前に出ると肩甲骨も前側に動き、胸椎が丸まりやすくなってしまうんですね。反対に肩甲骨を背骨側に寄せると背中が伸びやすくなり、胸椎の適切なカーブを保ちやすくなります。肩甲骨周辺の筋肉と胸椎の筋肉は連動しているため、どちらか一方だけでなく両方のバランスが重要なんです。
胸椎は頸部と腰部をつなぐ中間に位置していて、両方の土台として機能しています。首を支える筋肉の多くが胸椎や肋骨に付着しているため、胸椎の状態が頸部の安定性に影響するんですね。また胸椎の動きが悪いと腰椎に過剰な負担がかかることもあるわけです。
#姿勢維持 #猫背予防 #呼吸筋 #肩甲骨 #体幹の土台


胸椎が本来の適切なカーブを超えて丸まってしまう過剰後弯には、いくつかの原因があります。特に多いのが頭部の前方位で、スマートフォンやパソコンを見る時に顔が画面に近づくと頭が前に出てしまうんです。
頭の重さは約5キロもあるため、前に出た頭のバランスを取ろうとして背中が丸くなってしまうわけですね。また肩甲骨が前方に移動すると胸椎も連動して丸まりやすくなり、この状態が長く続くことで筋肉や関節が硬くなって元に戻りにくくなります。
胸の前側にある大胸筋が硬くなると、肩が内側に入る巻き肩の状態になってしまいます。大胸筋が縮んで硬いままだと肩甲骨を前側に引っ張り続けるため、胸椎の後弯も強くなってしまうんですね。
デスクワークで腕を前に出す姿勢が続くと大胸筋は常に縮んだ状態になり、巻き肩と胸椎の丸まりが定着してしまう可能性があります。この悪循環を断ち切るには、大胸筋のストレッチと肩甲骨周辺の筋肉を働かせることが大切です。
腰椎の動きが硬くなっていると、胸椎にも余計な負担がかかることがあるんです。背骨は全体でつながっているため、腰椎の柔軟性が不足すると胸椎がその分をカバーしようとして過剰に動いてしまうわけですね。骨盤周りの筋肉が硬いと背骨全体のバランスが崩れやすく、結果として胸椎の負担も増えてしまいます。
| 原因 | 胸椎への影響 |
|---|---|
| 頭部前方位 | 頭の重さで背中が丸まる |
| 肩甲骨前方移動 | 胸椎が連動して丸まる |
| 大胸筋の硬化 | 巻き肩から過剰後弯へ |
| 腰椎の柔軟性不足 | 胸椎への負担増加 |
胸椎の可動域を改善することは、腰痛予防にもつながると考えられています。胸椎が本来得意な回旋動作をしっかり行えれば、腰椎への負担を減らせるわけです。またスポーツのパフォーマンス向上にも胸椎の動きは重要で、ゴルフのスイングなど体を捻る動作では胸椎の柔軟性が鍵になります。
#胸椎可動域 #過剰後弯 #巻き肩 #腰痛予防 #体幹柔軟性
胸椎は背骨の中央部に位置する12個の椎骨で、肋骨と胸骨とともに胸郭を形成し、心臓や肺などの重要な臓器を守っています。起立筋群や多裂筋といった背筋群、横隔膜や肋間筋などの呼吸筋が付着しており、姿勢維持と呼吸の両方に深く関わっているんです。
胸椎は伸展、回旋、側屈という3つの主要な動きが可能で、特に回旋動作は背骨の中で最も得意な部分になります。肩甲骨との連動性も高く、肩甲骨の位置によって胸椎のカーブが変化するため、デスクワークなどで肩甲骨が前方に移動すると胸椎も丸まりやすくなってしまうわけです。
頭部の前方位や大胸筋の硬化、腰椎の柔軟性不足などが原因で胸椎の動きが制限されると、猫背や円背といった姿勢の問題だけでなく、腰痛や呼吸の浅さにもつながる可能性があります。胸椎の適切な可動域を保つことは、体全体のバランスを整え、日常生活やスポーツのパフォーマンス向上にも重要といえるでしょう。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/25/1/25_67/_article/-char/ja
https://seminar.realine.org/blogs/news/jhs2025_1
https://note.com/forpt/n/n5d9b03dcbfd1
https://backaging.com/dictionary/thoracic-vertebrae
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000769943/blog/bidA101025020.html